高校陸上は、トラックシーズンの終わりを迎える季節となりました。
シーズン最後の記録会が終わり、選手達は来年に向けての目標を立てている頃と思います。
そこで今回は部活動の時間をいただき、「インターハイに向けた冬季練習」についての講座を開催してきました。
私がチームに携わって、半年近くが経過しました。
日々の練習のサポートから始まり、数多くの大会帯同をして、チーム全体の見え方が変わったのが事実です。
冬季練習、言い方を変えると、インターハイの準備期間へ入る前に、チーム全体で現状把握をする必要があると思っていました。
より細かい状況把握をするために、事前アンケートを行っていまいした。
講座の最初は、アンケート結果から見えたチームの課題点について話をしました。
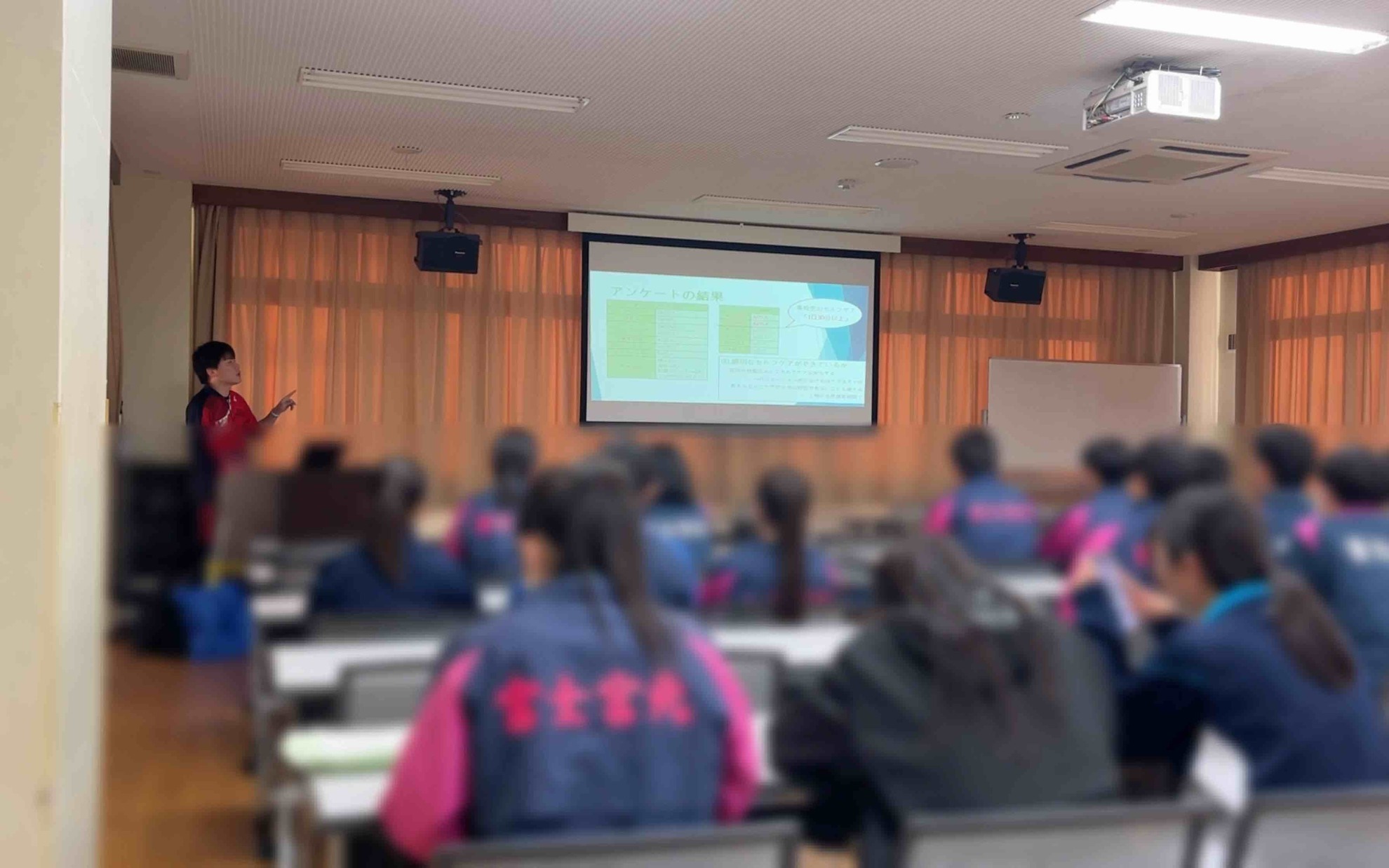
現状を知ってから目標を掲げることで、より具体性を持って練習する事ができます。
- 新人戦までに見えた課題点
- トレーナーとしての役割
- インターハイで勝つためには
など、冬季練習が正しくスタートできるように、事細かに説明しました。

これを基に冬季練習全体のスケジュールを説明し、
- 練習時期は区分けがされていること
- インターハイまでの時間が限られていること
- 冬季練習でケガが多い理由
など、今までの練習と冬季練習では要領が違うことを解説しました。
冬季練習の課題点は、チームや個人によって大きく異なります。
パーソナルアプローチは後々始めるとして、チーム全体の課題として、今回は「上半身の使い方」に着目して実技を計画しました。

上半身の中でも、私が今回重点に置いたのは「肩甲骨の動かし方」です。
投てき選手には馴染みがあると思いますが、走りや跳躍動作にも大きく関係する事です。
- 肩甲骨の役割とは?
- 肩甲骨がなぜ走りに繋がるのか?
- 肩甲骨を使うとケガが減らせる理由
などを、スライドや実際の動き、競技での実例を交えて説明し、この後の実技へ繋げました。

肩甲骨を動かす前に、今の姿勢や肩甲骨の動きを確認します。
モデルとして選手を前に出し、見本の動きを試してもらいます。
その選手の姿勢異常や動きの異常を説明し、選手同士で確認をしてもらいました。
このように、始める前に自分の状態を把握して、日頃から確認する習慣づけを教えました。
これが後々、強くなるために必要な能力となります。

肩甲骨の動きづくりでも同じように、モデルを前に出して実演し、

間違った方法を紹介、

それが競技にどう繋がるのかを説明、

お互いにチェックをしてもらいました。
中には陸上競技らしく、ハードルを使った肩甲骨の動きづくりも取り入れてみました。



最後に新しいセルフケアを紹介して、メンテナンスの補強に挑戦しました。
今回紹介した肩甲骨の動きづくりは、全体練習として取り入れることは基本的にありません。
言い換えれば、各自で取り組んでもらう形になるため、よりポイントを理解してもらう必要があります。
自分に必要な要素は何か?より競技力向上に繋がるモノは何か?
少しでも紹介した動きづくりを取り入れてくれると、私としては嬉しく思います。
今回の講座を準備する際に、チームトレーナーとしてではなく、治療家として物事を判断するよう注意しました。
選手に意識を変えてもらうためには、現実を突き付け、時には厳しくすることも必要です。
今まで私はチームトレーナーの立場として、個人的な意見を前面に出さないようにしてきました。
今回の講座内では、監督の言葉を随所で借りながら、私の意見を伝えるようにしました。
より良いチーム作りのためにも、どうしても伝えなければならないことも多くあったからです。
今回の講座を最後に、しばらくトレーナー活動は休憩となります。
活動自体は休憩に入りますが、冬季練習に向けて考えることは山程あります。
一度現場から離れて、今シーズンの振り返り、来シーズンへの目標を冷静に考えたいと思います。
この冬は、治療院でもトレーナー活動でも「パーソナル」に着目して活動したいと考えています。
トレーナー活動に戻る時に、チームがどのように変化しているのか楽しみです(^_^)








